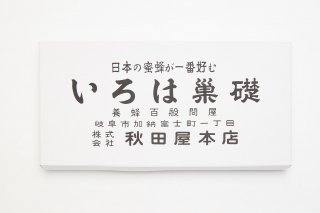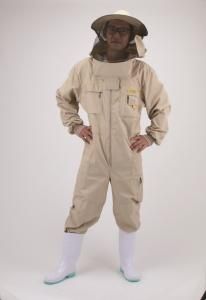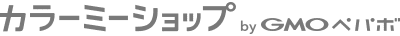Bee �ե��
�ߥĥХ�����֤����γڤ�����˪����
��4���θ�̾�Ų��ԡ�NPOˡ�͡��ޥ�ϥ����ץ��������Ȥγ�����

�ޥ�ϥ����ץ��������ȡ����ɤ���
����μ��Ǥϡ�JR����ض�γ������˪��Ҳ𤷤ޤ������������Ϥ�����Բ�ˤ�äƤ��ޤ�����
�����ϡ�̾�Ų��Ԥ��˲ڳ�����3���ܡ����ե����ӥ�䤪Ź��Ω���¤��Բ�ΰ�ѤǤ��������̱�Ȥϸ�������ޤ�������������Ĥ�ܤ�Ȫ�⡦�����������μ����ϡ������礭���̤���̤���9�����ƤΥӥ�β���ǡ��Բ�����˪���������Ƥ�����˪�졣

���Τ褦���Բ�˥ߥĥХ�����餷�Ƥ���Ȥ϶ä��Ǥ��������ơ�̪���Ȥʤ뿢ʪ�Ϥɤ��ˡ��͡��ʵ���������Ĥġ���˪������塪
�֥ߥĥХ�����ͤ���Ķ��Ť��ꡣ�פ�å��ե졼���˳�ư����Ƥ���NPOˡ�ͥޥ�ϥ����ץ��������Ȥ������μ����Ǥ�����˪�ץ��ǥ塼�����ξ��ɤ�����Բ��ɥߥĥХ����ͻҤ��Ƥ��������ޤ�����Ʊ�����ޥ�ϥ����ץ��������Ȥ���Ȫ����Τ��ä�Ƥ��Ϥ����ޤ���

�Բ�Τɿ����桪���餭�饬�饹ĥ�ꡣ���Υӥ�β���˥ߥĥХ�������Ȥ���������
���ʤ���˪��Ϥ�褦�Ȼפä��ΤǤ�����
��������ߥĥХ�����ˤϡ��Բ�����˪�β�ǽ��
COP10����ʪ¿�����������10���ݲ�ġˤ�̾�Ų��dz��Ť��줿2010ǯ������ˡ���ʪ�����ӥ����äȤ�狼��䤹�������Ƥ����ߥĥХ�����餹�뤳�Ȥ�פ��Ĥ��ޤ�����
�Բ�Υӥ�β���Ǥ���˪����������ä����Ȥʤä����ȤϤ����Ĥ�����ޤ������ΤȤ����ˡ�����ꥫ�ʤɤ�����ȤʤäƤ���˪�������ɸ�����CCD�ˤθ����ΤҤȤĤȵ����Ƥ����Τ������Ǥ����������ơ������������ﳲ������ˤ����Բ�Υӥ�β���Ǥ���˪������ζ�¤Ǽ�������Ƥ����ֶ�¥ߥĥХ��ץ��������ȡפ�����ޤ�����
�����ĥ�κݤ�ˬ�䤷������𤤡�̾�Ų��Ǥ�¸���ǽ���Ȼפ��Ϥ�ޤ�����

�ӥ�β���ˤ���ޤ��������ڤ˴�������Ƥ�����Ȣ�Ǥ���

���ޤ�����9�����ƥӥ�β���˽���ߥĥХ������Ǥ��������Ǥ���
����˪���äƤߤƳڤ�������꤬���ϡ�
���ɤ⤿���ؤδĶ����������ʥߥå����
˪������Ϥ�ơ����ο��뤵�����餷�����������ʤɳڤ������������Ƥ���ȴ����ޤ�����
��̪�δ�Ӥ��礭���Ǥ������������䤷�ơ��������������������������䤷���Ȥ��ϤȤƤ�ã����������ޤ�����������Ǥ⡣
�֤�Ʊ����������֤������ơ�NPO�Ȥ���̾�Ų��Ԥ�ǧ�ꤵ�줿���Ȥ��ӤǤ�����
�ޤ����Ķ����顢���ؤ����ڤʥߥå����ʤΤǡ����٥�����ǥߥĥХ����μ������ʤߡ������ꤷ���Ȥ����꤬������Ȥ��ΤҤȤĤǤ���
�äˡ����ɤ⤿���ζ�̣�˲Ф��դ��ơ��ܤ����Ƥ����Ȥ��ϻ�ʡ�Ǥ���
���κݡ��ϥ��ߥĤ����ۤ�Ԥ��ΤǤ������ͤ�����̣��Ǽ�����Ƥ����������㤤���Ƥ������������줬����ڤ��Ȥ�������������ޤ���
�ޥ�ϥ����ץ��������Ȥϸ���5̾�dz�ư���Ƥ��ޤ����ۡ���ڡ����ƥ��ץȤ˻�Ʊ�������ä��Ƥ��줿���С��⤤�ޤ����ߥĥ�����Ȥäƥ����ɥ���륢���ƥ����Ȥ��Ұ��ʤɥ��С����طʤ��͡��Ǥ���

���饭�����̪�������ޤ����������Ƥ�ֲ���פ�Ǥ��Ƥ��ޤ��͡�
�Բ����˪��Ǥ�����̪����¿��¿�ͤǤ����ߥĥХ������ϡ�����ģ�η�ʪ��Ω���¤�̾�Ų���μ��դޤ�����Ǥ��������Υ���̪��ΤäƤ��Ƥ���ޤ����ȤƤ⥭�쥤����������̪��̣�⤪�������Ǥ������Υ���̪��˭�٤ǡ���Ƥ˲֤��餯��̪���֤��餳�ܤ������ۤɤǤ�������γ�ϩ���������Ȥ��ƿ������Ƥ���Τ��Բ�Ǥ���˪�ξ�硢���פ�̪���ˤʤ�Ȼפ��ޤ�������¾�ϡ����Τ�����γ�ϩ���ˤʤäƤ������ɴ���ȡʤ��뤹�٤�ˤβ֤�Ť�̪���Ǥ���

�ӥ�ζ�θ���ˤϡ�̪���ˤʤ����Υ����餤�Ƥ��ޤ�����
����˪���������Ѥʤ��ȡ���ϫ�������ϲ��Ǥ�����
�Բ�����˪�ϡ���ŷŨ�ɤȡ�ʬ˪�ɤȤ��襤
���̤ξ�ǻ��餷�����Ȥ�̵���ΤǤʤ�Ȥ⤤���ޤ������ϲƤν뤵��������Ƥ����Τ����¤��ߤδ����Τۤ�������ǡ��䤨�ڤä�����Ȥ�����ʪ�ˤϸ������Ȥ������Ȥ�פ��Τ餵��ޤ��������ʤ�������ߤ����Ǥ�������ȡ���̪�Υ�������β����Ȥϡ��������ʤ�ʬ�Ĥ餤��Τ�����ޤ���
�ޤ������ॷ����̿�Ϥζ������ꤴ�蘆�ˤ���פȤ��ޤ�������ǯ�Ȥ����櫓�ǤϤ���ޤ���������Х��ν�����Բ�γ�ˤϤ���ޤ���
ʬ˪�������ޤ���Ȣ��ͶƳ�Ǥ��뤫�ɤ����⡢�Բ���˪�Ǥ����ڤʥݥ���ȤǤ���������ʬ˪�����Ȥ��ˤϤ��β���δ��Ĥ��˽��ޤäƤ����ΤǤ�������Ȣ��ͶƳ���ޤ��������̤Υӥ������Ǥ��ä��ꡢ���ܤˤĤ��˲ڳ��ޤ�����Ǥ��äƤ��ޤ��ȡ���𤬽Ф��ꡢ�������Ƥ��ޤ������⤢��ޤ��Τǵ���Ĥ������Ȥ����Ǥ���
NPO�α��ľ���������ˤϽ�ʬ�˺�̪������Ƥ��ʤ����Ȥ�����ޤ���
��������Υԡ����˿ͼ꤬�餺̪��̵�̤ˤ��Ƥ���Ȥ������Ȥ�����ޤ���

�ߥĥХ����Ĥ�����ϡ�����Ū����������
���������ɸ���Ƥ���������
�ߥĥХ����̤��ơ������Ķ��δ����ؤΰռ������
����ϡ���̱�λ��ä��äȿޤäƤ��������ȻפäƤ��ޤ���
�äˡ����ɤ⤿���Ȥ��οƤؤη��ؤϡ��Ķ����Ѳ�������Ƥ��ޤ�����δ�������Τ���ΰռ����μ�����Ƥ�餦���ä��������ʤȤ��ƽ��פ��ȹͤ��Ƥ��뤫��Ǥ���
���Τ���ˡ�ñ�ȤǤϤʤ�¾��Ʊ�ͤλ֤Τ������Τ�Ϣ�Ȥ��Ƥ������Ȥ�ʤ�Ƥ����ʤ���Фʤ�ʤ��ȻפäƤ��ޤ���
����ϡ���ȤƤ����ͤ����䤷�Ƥ������Ȥˤ�Ĥʤ���ȴ��Ԥ���Ȥ����Ǥ���

2018ǯ5��18�����
- ��1���츩����ԡ����츩Ω�������ȹ����ع����ֺ餫�ߤĤФ������ɤγ�����
- ��2���츩���練����Į���ʳ��˥��ե��������ݥ쥤�����ë��Ĺ
- ��3���츩����ԡ���̣����˪�ȡ��������
- ��4���θ�̾�Ų��ԡ�NPOˡ�ͥޥ�ϥ����ץ��������Ȥγ�����
- ��5���θ���¿������Į����̣����˪�ȡ�����ػҤ���
- ��6���ٻ����Ϳ�ԡ��ʳ��˥������������ݥ졼�����Ȫ�Ƥ���
- ��7���θ�ð�������ߥ������������������
- ��8���츩��Ȭ������Į��ͧ���������ҡ����������
- ��9���츩����ԡ��ǥ��å�������ɥ�ʳ��� ��ƣ��������
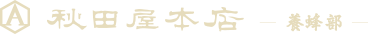
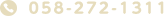
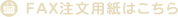
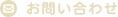


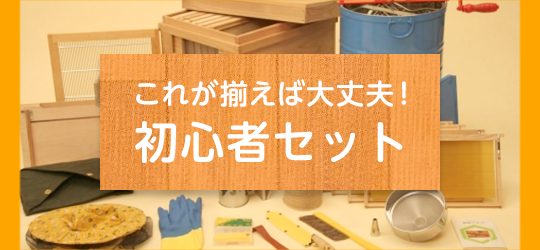


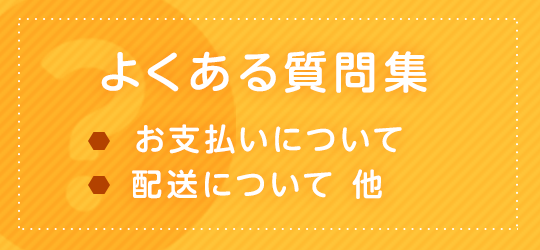

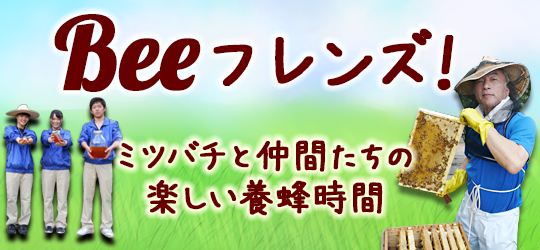
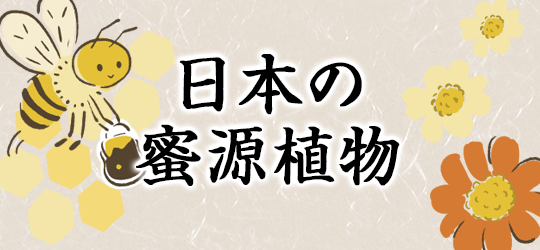
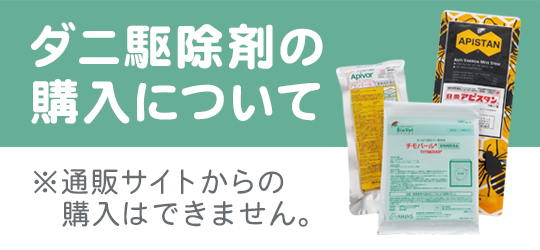



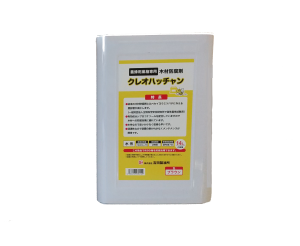

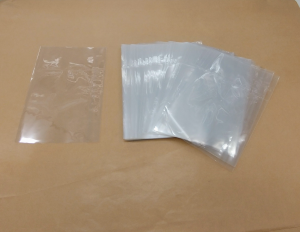



![�ӡ��֥�ɥץ饹��ʴ����[̪˪�Ѻ�����������Ѳ�ʴ]�Ի�ʧ��ˡ�����쥸�å����ѡ�](https://img07.shop-pro.jp/PA01365/745/product/171313303_th.jpg?cmsp_timestamp=20221105170415)